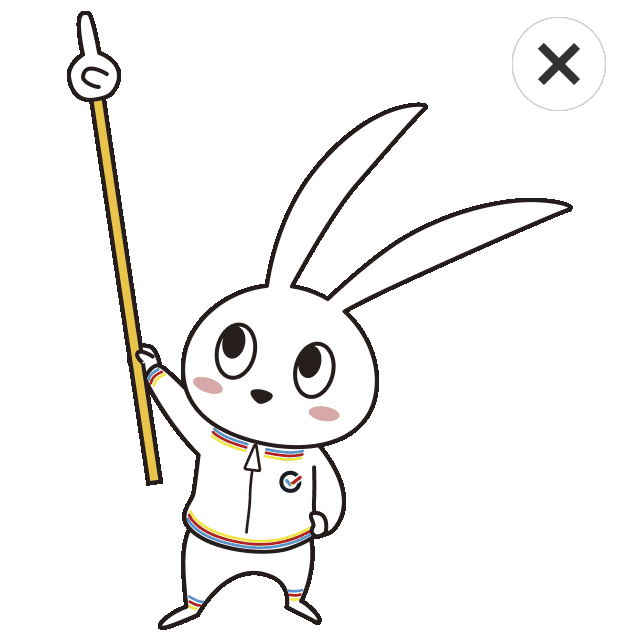冬の厳しい寒さや雪から、丹精込めて育てた大切な庭木を守る「冬囲い」。
毎年冬が近づくと「今年はどうしようか」と悩む方も多いのではないでしょうか。しかし、具体的な方法や効果が分からず、結局手付かずのまま冬を迎えてしまうことも。
自己流で挑戦してみたものの、良かれと思った作業が裏目に出て、かえって木を傷める失敗に繋がるのは避けたいものです。
そもそも、うちの木に冬囲いは本当に必要なのか?そんな疑問にもお答えします。
この記事では、庭木の冬囲いに関する失敗例と成功のコツ3選を、具体的なデータや出典を交えながらプロが詳しく解説します。
費用や専門業者に依頼する方法についても紹介しますので、大切な庭木と長く付き合うための冬支度の参考にしてください。
この記事で分かる4つのポイント
- 庭木の冬囲いがなぜ必要なのか、その具体的な理由と効果
- 初心者が陥りがちな冬囲いの失敗例とその科学的な対策
- 庭木の冬囲いを成功に導くための3つの重要なコツ
- 自分で作業する際の限界と専門業者に依頼するメリット
- 庭木の冬囲いが必要とされる理由
- 庭木の冬囲いがもたらす効果とメリット
- 知っておきたい庭木の冬囲いの種類
- 簡単な方法と具体的な作業内容
- やりがちな庭木の冬囲いの失敗例
- 庭木の冬囲いを成功させるコツ3選
- 自分で作業する場合の限界と注意点
- プロに依頼する場合の費用相場
- プロの作業と専門業者へ依頼する価値
■ 庭木の冬囲い作業に必要な成功のコツ3選とその失敗例の総括
庭木の冬囲いの基本|失敗例と成功のコツ3選
庭木の冬囲いが必要とされる理由
庭木の冬囲いは、植物が冬の厳しい環境を乗り越えるために不可欠な作業です。特に寒冷地や積雪の多い地域では、冬囲いの有無が庭木の生死を分けることもあります。
主な理由として、まず「積雪による枝折れの防止」が挙げられます。雪は見た目以上に重く、国土交通省の資料によると、新雪でも1㎥あたり50kg~150kg、湿った雪になると300kg~500kgもの重量に達します。
この重みが枝に集中すると、太い枝でも折れてしまい、樹形が大きく崩れます。特に葉の表面積が広い松などの常緑樹は雪が積もりやすく、注意が必要です。
次に、「寒風や霜からの保護」も大きな目的です。冬の乾燥した風は庭木の枝葉から水分を奪って乾燥害を引き起こします。
また、放射冷却による霜は植物の細胞内の水分を凍らせて膨張させ、細胞壁そのものを物理的に破壊することで新芽や花芽に深刻なダメージを与え、春の開花を妨げる可能性があります。
さらに、「凍結による幹割れの防止」も見逃せません。日中に太陽光で暖められた樹皮が、夜間の急激な冷え込みで凍結と融解を繰り返すと、幹が縦に裂ける「凍裂(とうれつ)」という現象が起こります。これを防ぐため、幹に保護材を巻く作業が有効です。
最後に、「害虫の越冬対策」という側面もあります。藁などを幹に巻く「こも巻き」は、害虫をそこに誘い込み、春先に藁ごと処分することで効率的に駆除するための伝統的な知恵です。
これらの科学的根拠に基づいた理由から、庭木の健康を維持するためには、冬囲いがとても大切なのです。
冬囲いをしないとどうなるのか?
もし庭木の冬囲いを怠った場合、様々な被害が発生する可能性があります。見た目が悪くなるだけでなく、最悪の場合、庭木が枯れてしまう原因にもなり得ます。
最も頻繁に起こる被害は、雪の重みによる「枝折れ」です。一度折れた太い枝は再生せず、その傷口から木材腐朽菌などの病原菌が侵入するリスクが格段に高まります。
樹形が大きく損なわれると、回復には数年単位の管理が必要になるか、元には戻らないかもしれません。一度崩れた樹形は、庭全体の印象を大きく左右してしまいます。
また、寒さや乾燥による被害も深刻です。特に、植え付けてから2~3年以内の若木や、温暖な気候を好む樹木は、冬の厳しい環境に耐えられず、枝先から枯れ込んでしまうことがあります。
葉が茶色く変色したり、春に新芽が出なかったりするのは、冬の間に細胞レベルで受けたダメージが原因であるケースが少なくありません。一度弱った木は回復が遅れるだけでなく、翌シーズン以降の病害虫に対する抵抗力も低下してしまいます。
幹が凍結によって裂ける「凍裂」が発生すると、木の内部にある維管束(水や養分を運ぶ管)が露出し、木の生命活動に直接的な影響を及ぼします。そこから腐朽菌が侵入すれば、木の内部から腐敗が進み、数年かけて衰弱し、枯死に至ります。
さらに、カイガラムシやミノムシなどが樹皮の隙間で越冬しやすくなり、春になると活動を再開し、大量発生して庭木を弱らせる原因となります。
これらの被害は一度発生すると対処が難しく、専門知識が必要になる場合が多いため、冬囲いは未来の庭への「重要な投資」と考えることが大切です。
庭木の冬囲いがもたらす効果とメリット
適切な冬囲いは、冬の様々なリスクから庭木を保護し、健やかな成長を促す多くのメリットがあります。
最大のメリットは、冬の物理的なダメージから庭木を確実に守れる点です。最大500kg/㎥にもなる雪の重さによる枝折れや、強風、幹の凍裂といった被害を未然に防ぎます。
これにより、庭木本来の美しい樹形を維持し、春からのスムーズな生育を助けます。美しい樹形は庭全体の景観価値を高め、ひいては不動産価値の維持にも繋がります。
次に、植物の生理的な負担を軽減する効果があります。冬の乾燥した寒風や霜から枝葉を保護することで、水分の過度な蒸散を防ぎ、乾燥害を最小限に抑えます。また、急激な温度変化から花芽や新芽を守ることで、春には豊かな花や新しい葉を楽しめます。
さらに、病害虫の発生を抑制する効果も期待できます。特に「こも巻き」は害虫を誘い出して駆除する伝統的な手法で、ある造園専門家は「農薬に頼らない環境に優しい害虫駆除(IPM:総合的病害虫管理)の一環としても再評価されています」と指摘しています。
精神的なメリットとしては、大切な庭木を守っているという安心感が挙げられます。冬の間、庭木が傷む心配が減り、春の訪れをより一層楽しみに待つことができるでしょう。丹精込めて育てた木々を守る作業は、ガーデニングの喜びを深める一つの要素とも言えます。
知っておきたい庭木の冬囲いの種類
庭木の冬囲いには、対象となる木の種類や大きさ、地域の気候に応じて様々な方法が存在します。
幹巻き(みきまき)
若木やカエデ、サルスベリ、果樹など樹皮の薄い木の幹を、わらや専用テープで巻き、凍裂、害虫、動物の食害から守ります。日中の寒暖差が激しい地域で特に有効です。
枝吊り(えだつり)
積雪量の多い地域で重要な作業で、中心の柱から放射状に張った縄で枝を吊り、雪の重みを分散させて枝折れを防ぎます。石川県金沢市の兼六園で行われる「雪吊り」は、江戸時代から続く伝統技術として有名です。また、景観を美しく保つ効果もあります。
(出典:石川県金沢城・兼六園管理事務所「兼六園の雪吊り」
https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/event/detail_50425.html)
こも巻き
わらで編んだ「こも」を幹に巻き、マツカレハなどの害虫を誘い込み越冬させます。春の「啓蟄(けいちつ)」(3月5日頃)の時期にこもごと処分し、害虫の発生を抑制します。近年ではその効果について専門家の間でも議論がありますが、伝統的な冬の景観として今も広く行われています。
合掌囲い(がっしょうがこい)
竹や木の棒を合掌造りの形に組み、ネットなどを被せて木全体を覆います。ボタンやシャクナゲ、アジサイなど、枝がもろく雪の圧力で折れやすい低木を守るのに適しています。特に新梢に花芽がつく植物は、枝先を保護することが翌年の開花に繋がります。
ネット囲い・敷きわら
寒冷紗などのネットで低木全体を覆い、霜や寒風から守ります。また、株元にわらや腐葉土を厚さ5~10cm程度敷く「敷きわら(マルチング)」は、土の凍結を防ぎ根を保護します。冬の間に風で飛ばされたり、沈み込んだりすることもあるため、時々厚さを確認するとより効果的です。
簡単な方法と具体的な作業内容
全ての庭木に大掛かりな冬囲いが必要なわけではありません。比較的小さな低木などには、簡単な方法で冬越し対策が可能です。
最も手軽なのは、株元をわら等で覆う「マルチング」です。大手園芸資材メーカーによると、土の凍結や乾燥、雑草の抑制に効果があります。
作業は、株元の雑草を取り、厚さ5~10cmほど資材を敷くだけです。幹に密着させると蒸れて病気の原因になるため、少し隙間を空けましょう。
背の低い木には「寒冷紗や不織布による被覆」が有効です。植物全体にふんわりと被せ、裾をピンで固定します。通気性があり、約50%の遮光率で植物への負担が少ないのが利点です。ただし、雪が多い地域では、布の上に積もった雪の重みで枝が折れないよう注意が必要です。
よりしっかり保護するなら「支柱を使った簡単な囲い」もあります。数本の支柱を植物の周りに立てて縄を巻き、雪が直接積もるのを防ぎます。
(出典:株式会社フマキラー「園芸におけるマルチングとは?効果や使用方法、注意点をわかりやすく解説」
https://fumakilla.jp/foryourlife/516/)
効果的に庭木の冬囲いを行うには、プロの業者に依頼して、専門的なサービスを受けることが推奨されます。プロの持つ専門的な知識と経験値で、確実に庭木の冬囲いに対応してくれます。
熟練の職人による最高級の仕事
「Kirei One」では、上に紹介した庭木の冬囲いサービスを全都道府県で行っており、専門知識を持つ、経験値の高いスタッフを揃えています。
様々なお客様から依頼をいただいており、庭木の冬囲い以外にも清掃に関する技術と経験・お客様満足度は清掃業界内でも随一という自負を持っています。
常に適正なお見積もりを心掛けていますので、新たに庭木の冬囲いの作業を考えている方は、ぜひ一度ご相談下さい。
庭木の冬囲いの実践|失敗例から学ぶ成功のコツ3選
やりがちな庭木の冬囲いの失敗例
良かれと思った冬囲いが、かえって木を傷つけてしまう失敗例を紹介します。
一つ目は、「作業のタイミングが不適切」なことです。開始が早すぎると内部が蒸れて病気の原因に、遅すぎると初雪などで木がダメージを受けてしまいます。
二つ目は、「縄の縛り方が強すぎる、または弱すぎる」ことです。きつすぎると樹皮の下にある形成層という細胞層を傷つけ、緩すぎると雪の重みで外れてしまい、保護機能を果たせません。
三つ目は、「資材の選択ミス」です。通気性のないビニールシートで覆うと、内部が高湿度になり木を弱らせます。
四つ目は、「春になっても外し忘れる」ことです。暖かくなっても囲いを付けたままにすると、風通しが悪く病害虫の温床になったり、新芽の成長を妨げたりします。
五つ目は、「雪の量を甘く見ている」ことです。特に暖冬予報の年に油断しがちですが、局地的なドカ雪は起こり得ます。簡易的な囲いでは、想定外の積雪量に耐えきれず、結局枝が折れてしまうことがあります。
最後に、「庭木の特性を無視した画一的な作業」も失敗の原因です。寒さに強いマツと弱いツバキでは必要な保護が異なります。
庭木の冬囲いを成功させるコツ3選
庭木の冬囲いを成功させ、大切な木を冬のダメージから守るためには、いくつかの重要なコツがあります。
-
適切な時期を見極める
作業の開始と終了のタイミングが重要です。開始は最低気温が摂氏5度を下回る日が続く11月下旬~12月上旬が目安。北海道や東北では10月下旬から、関東以西では12月に入ってからと、地域差を考慮しましょう。囲いを外すのは、遅霜の心配がなくなる3月中旬~4月上旬です。
-
樹木の種類と状態に合わせた方法を選ぶ
木の特性に合わせ、冬囲いの方法や強度を調整します。葉に雪が積もりやすい常緑樹は枝吊り、落葉樹は枝をまとめる作業が中心です。植えたばかりの若木や、キンモクセイなど寒さに弱い木は、幹巻きなどでより手厚く保護しましょう。
自分の庭木がどの程度の耐寒性を持つか、耐寒性ゾーン(ハーディネスゾーン)などを調べてみるのも有効です。また、その年の夏の気候や木の健康状態も考慮に入れましょう。
-
適切な資材と正しい技術を用いる
目的に合った資材と正しい技術が不可欠です。ビニールは避け、わらや寒冷紗など通気性のある資材を使いましょう。古い縄を使う場合は、腐食して強度が落ちていないか事前に確認します。
技術面では縄の結び方が重要です。プロも多用する、固定しやすく解きやすい「男結び(いぼ結び)」を練習しておくと良いでしょう。
自分で作業する場合の限界と注意点
まず、物理的な限界として「高所作業の危険性」が挙げられます。厚生労働省の統計でも、はしごや脚立からの墜落・転落による労働災害は後を絶ちません。
家庭ではさらにリスクが高く、高さが2mを超えるような作業は重大事故に繋がるため避けるべきです。作業前には道具の点検を行い、滑りにくい靴や手袋を着用するなど、安全対策を徹底しましょう。
また、適切な道具が揃っているかも重要です。短い脚立や切れ味の悪いハサミで無理に作業すると、怪我や作業品質の低下に繋がります。
次に、専門知識と技術の限界です。間違った方法では、保護するどころか木を傷つける可能性があります。また、作業にかかる時間と労力、資材を揃える手間も考慮すべきです。
これらの限界から、DIYでの注意点は「決して無理をしない」ことです。危険や難しさを感じたら、迷わず専門業者に相談しましょう。
(出典:厚生労働省 「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002150049.pdf)
プロに依頼する場合の費用相場
専門業者に冬囲いを依頼する場合、費用は複数の要因で変動します。
費用は「職人の日当」か「木1本あたりの単価」で計算されるのが一般的です。職人1人の日当相場は15,000円~30,000円程度で、これに資材費などが加わります。木1本あたりの単価は、高さによって決まるのが通常です。
- 高さ3m未満の低木
3,000円~8,000円程度
- 高さ3m~5mの中木
8,000円~20,000円程度
- 高さ5m以上の高木
20,000円~(要見積もり)
これは目安であり、木の枝ぶりや作業方法(簡単な幹巻きか複雑な雪吊りか等)で料金は大きく変わります。
正確な費用は2~3社から相見積もりを取り、料金の内訳や春の撤去作業が含まれるか、万が一の事故に備えた損害賠償保険に加入しているかなどを確認すると安心です。
良い見積もりは、作業内容だけでなく、使用する資材の種類や量まで具体的に記載されています。
プロの作業と専門業者へ依頼する価値
費用をかけて専門業者に依頼するには、それに見合う確かな価値があります。
最大の価値は「専門性と確実性」です。あるベテラン庭師は冬囲いを「木の骨格を読み、雪の流れを予測し、春の芽吹きを手助けする木との対話」と語ります。このようなプロの視点と、機能美を備えた技術は素人には真似できません。
適切な作業は、木の寿命を延ばし、長期的に見て庭の資産価値を高めます。それは、将来にわたって美しい景観を維持するための、賢明な先行投資と言えるでしょう。
「安全性と効率性」も大きなメリットです。プロは安全管理を徹底し、専用の道具で迅速に作業を終えるため、自分で危険な作業をする必要がありません。
また、「総合的な庭木管理のアドバイス」がもらえる点も見逃せません。作業の際に庭木全体の健康状態を診断し、剪定や病害虫対策などについて助言を得られます。
最終的にはプロに任せる「安心感」が得られます。専門業者への依頼は、コストではなく、大切な庭木を守るための賢明な選択と言えるでしょう。
庭木の冬囲い作業に必要な成功のコツ3選とその失敗例の総括
庭木を効果的に冬囲いしたい方にとって、プロの業者に依頼して、専門的なサービスを受けることは検討すべき内容です。
実際に利用されるお客様の視点から考えると、庭木の冬囲いがしっかりと実施され、安心感が上がる利点は大きいです。
また、庭木の冬囲い作業を丁寧に行うことによって、お住まいになる方の満足感にも繋がります。
実際に毎日利用される方にとって、これらの存在がいかに効果的か、お分かりになったと思われます。
- 庭木の冬囲いは重さ500kg/㎥にもなる雪の枝折れを防ぐ
- 冬の寒風や霜から枝葉や花芽を保護する
- 幹が凍結で裂ける凍裂を防ぐ効果がある
- 農薬に頼らない害虫の越冬対策としても有効である
- 冬囲いをしないと樹形が損なわれ病原菌侵入のリスクが高まる
- 寒さに弱い木は細胞レベルでダメージを受け枯れる可能性がある
- 作業開始が早すぎると蒸れてカビや病気の原因になる
- 春に外し忘れると病害虫の温床になるため注意が必要
- 縄の縛り方が強すぎると形成層を傷つけ木の成長を阻害する
- 通気性のないビニール資材の使用は絶対に避けるべき
- 成功のコツは最低気温5度を目安に適切な時期を見極めること
- 木の原産地や特性に合わせた方法を選ぶことが重要
- プロも使う「男結び」など正しい技術を用いることが効果を最大化する
- 高さ2m以上の高所作業は重大事故のリスクがあり危険
- 想定外のドカ雪も考慮し、強度を確保することが大切
- DIYの場合は安全対策と適切な道具の準備を徹底する
- 専門業者への依頼は確実性と安全性が高く結果的に価値がある
- 費用を知るには複数の業者から相見積もりを取ることが推奨される